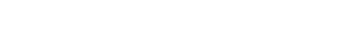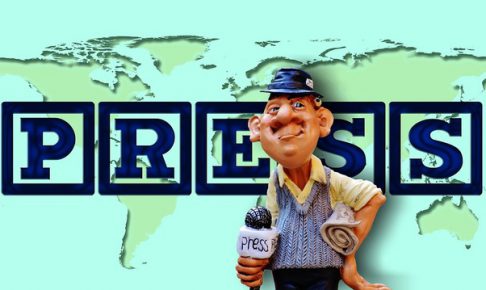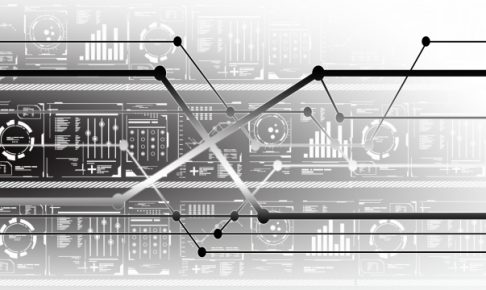関東大震災は、1923年(大正12年)9月1日11時58分に発生した大地震です。日本の近代化された首都圏を直撃し、甚大な被害をもたらしました。
発生日時と規模
発生日時: 1923年(大正12年)9月1日 午前11時58分
震源: 神奈川県西部から相模湾にかけての地域
マグニチュード: 7.9と推定
最大震度: 震度6(現在の震度階級では震度7に相当する揺れがあったとも言われています)
被害の特徴
関東大震災の被害は、その発生時刻と複合的な要因によって拡大しました。
火災による被害:
地震の発生時刻が昼食の準備時間と重なり、多くの家庭で火が使われていました。
震災当日、日本海を北上する台風の影響で強い風が吹いており、この強風によって各地で発生した火災が広範囲に燃え広がりました。
特に東京では、木造住宅の密集地帯で「火災旋風」と呼ばれる巨大な炎の渦が発生し、多くの犠牲者を出しました。死者・行方不明者約10万5000人のうち、9割近くが火災による焼死だったとされています。
建物の倒壊:
神奈川県から千葉県南部にかけての地域では、強い揺れによって多くの家屋が倒壊しました。
横浜市や東京市(当時)の市街地も大きな被害を受けました。
土砂災害と津波:
神奈川県小田原市の根府川駅では、大規模な山崩れが発生し、停車中の列車が海に転落する事故が起きました。
震源が海底であったため、静岡県の熱海で最大12m、千葉県の館山で最大9mの津波が観測されました。
影響と教訓
関東大震災は、その後の日本の防災・都市計画に大きな影響を与えました。
「防災の日」の制定: 震災の教訓を忘れないため、毎年9月1日は「防災の日」と定められています。
都市の復興と耐震化: 震災後、東京では大規模な区画整理が行われ、公園や広い道路が整備されました。また、耐震・耐火建築の重要性が認識され、建物の不燃化や耐震化が進められるきっかけとなりました。
デマの拡散と社会の混乱: 震災後には、「朝鮮人が井戸に毒を入れた」といった根拠のないデマが流布し、社会の混乱を招きました。これが原因で、多くの朝鮮人や中国人が自警団などによって殺害されるという痛ましい事件も発生しました。この歴史は、災害時の情報リテラシーや社会の脆弱性を考える上で重要な教訓となっています。
開業2002年。
23年の歴史を誇る情報サイト、NJI!
会員専用のサイトでは、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、
市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等を
タイムリーに情報提供。
テーマ株やIPOまで、相場の流れを掴み、
各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。