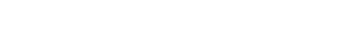これまでのコメ政策:減反政策
減反政策は、コメの生産過剰による価格下落を防ぐため、1970年代から本格的に導入されました。これは、国が生産目標量を設定し、農家に作付け面積の削減(減反)を奨励・義務付けることで、コメの生産量を調整する仕組みでした。
目的: コメの安定した価格を維持し、農家の所得を確保すること。
手段: 減反を行った農家に対し、転作作物(麦、大豆など)への補助金を支給すること。
この政策は、コメの価格を安定させる一方、以下のような課題も抱えていました。
生産意欲の低下: 補助金に頼ることで、市場の需要に応じた生産や経営努力が阻害されるという指摘。
食料自給率の低下: 自給率の高いコメの生産が抑制されることで、日本の食料自給率(カロリーベース)が低下する一因となった。
市場の硬直化: 行政が生産量を決めるため、消費者のニーズ(加工用米、輸出用米など)に対応しづらい側面があった。
コメ政策の転換
2018年、政府は減反政策を廃止し、新たなコメ政策へと舵を切りました。この転換は、生産者自身が市場の動向や消費者のニーズに応じた生産を行うことを促すもので、以下のような特徴があります。
生産数量目標の廃止: 国が生産量を決めるのではなく、生産者が自らの経営判断に基づいて作付けを行う方針に転換。
需要に応じた生産: 主食用米だけでなく、加工用米、飼料用米、輸出用米など、多様なニーズに応じた生産を支援。
農地集積・規模拡大の推進: 耕作放棄地を集約する「農地バンク」の機能強化などにより、大規模で効率的な農業経営を支援。
輸出支援の強化: 海外の需要開拓や、輸出用米の生産拡大に取り組む農家への支援を拡充。
転換による影響
この政策転換は、農業生産者と消費者双方に様々な影響を与えています。
【生産者への影響】
競争激化と経営リスクの増大: 国による価格の下支えがなくなるため、価格変動のリスクを直接負うことになります。市場の動向を読み、生産する作物を選択する経営力がより重要になります。
規模拡大と効率化の進展: 大規模農家や農業法人が、効率的な生産を通じて競争力を高める一方で、小規模な兼業農家は経営が難しくなる可能性があります。
多様な作物の生産拡大: 補助金の見直しにより、飼料用米や米粉用米など、主食用米以外の生産が増加しています。
【消費者への影響】
価格の変動: 需給のバランスによって価格が大きく変動する可能性があります。過去には、作柄不良などによりコメの価格が高騰した事例もあります。
選択肢の多様化: 銘柄米や機能性米など、消費者の嗜好に合わせた多様なコメが市場に出回るようになります。
まとめ
コメ政策の転換は、長年続いた行政主導の生産調整から、市場の原理に基づいた生産へと移行するものです。これは、国際的な競争力を高め、食料自給率の向上にも繋がる可能性を秘めていますが、同時に生産者にはより高い経営能力が求められ、消費者にとっても価格変動などの影響を受けることになります。
2001 ニップン
2211 不二家
2212 山パン
2282 日ハム
2700 木徳神糧
4005 住友化
4025 多木化
4031 片倉コープ
4992 北興化
4995 サンケ化
4996 クミアイ化
4997 日農薬
6310 井関農
6316 丸山製
6326 クボタ
7272 ヤマハ発
9305 ヤマタネ
開業2002年。
23年の歴史を誇る情報サイト、NJI!
会員専用のサイトでは、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、
市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等を
タイムリーに情報提供。
テーマ株やIPOまで、相場の流れを掴み、
各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。