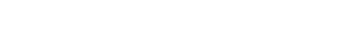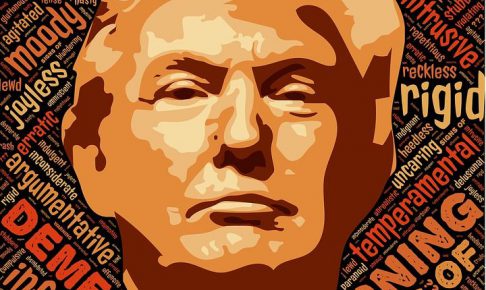ステーブルコイン(Stablecoin)とは、その名の通り「安定した(stable)」価格を持つように設計された暗号資産(仮想通貨)のことです。
通常のビットコインやイーサリアムなどの暗号資産は、価格変動(ボラティリティ)が非常に大きいため、決済や日常的な取引に使うことが難しいという課題がありました。
この課題を解決するため、法定通貨(米ドルや日本円など)や金(ゴールド)といった特定の資産と価格が連動するように設計されたのがステーブルコインです。これにより、暗号資産のメリットである「迅速な送金」「取引の透明性」などを享受しつつ、価格の安定性を確保しています。
ステーブルコインの主な種類
ステーブルコインは、価格を安定させる仕組みによって主に以下の4つに分類されます。
法定通貨担保型
仕組み: 米ドルやユーロ、日本円などの法定通貨を、発行額と同等、もしくはそれ以上の額で保有することで、価値を担保します。
特徴: 担保資産が明確であるため、最も信用度が高いとされています。市場に流通しているステーブルコインの多くがこのタイプです。
代表例: USDT(Tether)、USDC(USD Coin)、BUSD(Binance USD)など。
暗号資産担保型
仕組み: ビットコインやイーサリアムなどの暗号資産を担保として、価値を維持します。担保となる暗号資産の価格変動リスクを考慮し、発行額よりもはるかに多くの担保を預け入れる「超過担保」という仕組みが一般的です。
特徴: 分散型(特定の管理者がいない)で発行されることが多いのが特徴です。
代表例: DAI(Dai)など。
商品担保型(コモディティ型)
仕組み: 金(ゴールド)や銀などの商品を担保として、その価値に連動するように設計されています。
特徴: 物理的な資産に裏付けられているため、価値の安定性が高いとされています。
代表例: XAUT(Tether Gold)など。
無担保型(アルゴリズム型)
仕組み: 特定の資産を担保とせず、アルゴリズム(プログラム)によって自動的にコインの供給量を調整し、価格を安定させようとします。
特徴: 担保が不要なため柔軟性が高い一方で、アルゴリズムの設計に依存するため、信用性が低く、価格が不安定になるリスクも指摘されています。
代表例: かつて存在したUST(TerraUSD)など。
日本におけるステーブルコインの動向
日本では、2023年6月に改正資金決済法が施行され、ステーブルコインは「電子決済手段」として位置づけられました。これにより、国内でステーブルコインを発行できる主体が、銀行や信託会社、資金移動業者などに限定され、利用者保護のルールも整備されました。
これにより、日本円を担保とした「円建てステーブルコイン」の発行・流通も進むと期待されています。実際に、日本のベンチャー企業などが円建てステーブルコインの発行に向けた動きを見せています。
2181 パーソルHD
2497 UNITED
3626 TIS
3747 インタートレ
3853 アステリア
4072 電算システム
4373 シンプレクス
4499 スピー
6758 ソニーG
8306 三菱UFJ
8316 三井住友FG
8411 みずほFG
8473 SBI
8746 unbank
9432 NTT
9449 GMO
開業2002年。
23年の歴史を誇る情報サイト、NJI!
会員専用のサイトでは、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、
市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等を
タイムリーに情報提供。
テーマ株やIPOまで、相場の流れを掴み、
各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。