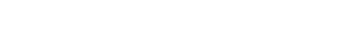国立環境研究所では、実際にヒアリの生態を把握するための飼育実験が行われています。これは、日本で初めてのヒアリ専門の実験施設で行われており、NHKの報道(2025年3月14日)でもその様子が紹介されています。
国立環境研究所におけるヒアリ飼育実験の目的と内容:
防除研究の推進:
薬剤選定・開発: 防除に適した薬剤の選定や、新たな防除方法・薬剤の開発が主な目的です。ヒアリの行動やコロニーの特性を理解することで、より効果的なベイト剤や液剤の開発に繋げます。
薬剤感受性試験: 各種薬剤に対するヒアリの感受性を評価し、どの薬剤が効果的であるかを明らかにします。過去の研究では、フィプロニルがヒアリに対して非常に強い薬効を持つことが示されています。
昆虫成長制御剤(IGR剤)の研究: アリの変態を妨げるIGR剤の効果についても研究が進められています。
早期発見・AI開発:
画像認識AIの精度向上: カメラで撮影した画像からヒアリの有無を判断するAIの精度向上も進められています。これにより、より迅速かつ正確なヒアリの発見が可能になります。
生態学的研究:
日本の環境下での特徴把握: 日本の環境条件下でのヒアリの繁殖、摂食、行動などの生態的特徴を詳細に観察・分析することで、日本での定着リスクや拡大経路を予測する基礎データを得ます。
コロニーレベルでの防除効果確認: 人工コロニーを用いた実験により、防除策がコロニー全体にどのように作用するかを確認しています。
普及啓発活動:
標本作成: 啓発活動のためにヒアリの標本を作成し、港湾関係者や自治体への寄贈も検討されています。これにより、一般の人々や関係者がヒアリを正しく認識し、早期発見に繋がるようにしています。
安全対策:
ヒアリは「特定外来生物」であり、強い毒性を持つため、飼育には厳重な安全対策が施されています。
厳重な飼育施設: 施設は厳重に管理され、ヒアリの逸出を防ぐために、容器は三重構造になっていたり、蓋には目の細かい金網が溶接されているなど、多重の対策が講じられています。
環境省の許可: 当然のことながら、国立環境研究所は環境省の「特定外来生物飼養等許可」を得て、これらの研究を実施しています。
国立環境研究所は、ヒアリ問題に対する日本の最先端の研究機関として、その生態解明と効果的な防除対策の確立に貢献しています。
開業2002年。
23年の歴史を誇る情報サイト、NJI!
会員専用のサイトでは、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、
市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等を
タイムリーに情報提供。
テーマ株やIPOまで、相場の流れを掴み、
各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。